interview
/home/accom/danceplusmag.com/public_html/manage/wp-content/themes/ac_temp_2/content-single.php on line 23
">
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on bool in /home/accom/danceplusmag.com/public_html/manage/wp-content/themes/ac_temp_2/content-single.php on line 23
きたまり × 芳賀直子 対談『結婚』 原作と新作のあいだ
2012年10月7日

Taka a chance project 029 KIKIKIKIKIKI新作『結婚』『戯舞』
日時: 2012年12月14日(金)~16日(日)
会場: アイホール(兵庫県伊丹市)
URL:http://www.aihall.com/lineup/gekidan21.html
お話に出てくる作品や人のことを知るために
-「ディアギレフのバレエ・リュス展 舞台美術の革命とパリの前衛芸術家たち1909-1929」1998年@セゾン美術館、滋賀県立近代美術館
-「舞台芸術の世界〜ディアギレフのロシアバレエと舞台デザイン〜」展 2007年@北海道立釧路芸術館、京都国立近代美術館、東京都庭園美術館、青森県立美術館
※上記2点のカタログは、開催美術館や公立図書館で所蔵・閲覧などの可能性をおたずねください。
-芳賀直子著『バレエ・リュス その魅力のすべて』国書刊行会2009

◆ 『結婚』—出会いから目標へ-
きた:実は『結婚』をやりたいなと思ったのはかなり早くて大学生の頃から。本当は卒業制作でやりたかったんです。もちろん「今できるわけがない。絶対無理」と諦めましたが。それで『プロポーズ』という作品をつくったんですよ(笑)。
芳賀:『プロポーズ』と『結婚』と同時上演なんて、個人的には見てみたいですけどね。(笑)きっかけは何だったんですか。
きた:大学の頃、ダンスのビデオを手当たり次第借りていたので、その中で『結婚』を見たのだと思います。確かロイヤル・バレエのバージョンだったかな。
芳賀:ではオリジナルですね。1966年にニジンスカ本人が再振付をしていますから。それが今でもオリジナルに近いんです。
きた:なるほど。バレエ・リュスでは他に、『パラード』なんかも覚えています。1920年代の前後って面白いじゃないですか。
芳賀:ヴィヴィッドで多面性があり。
きた:誰をピックアップしてもつながってゆく。
芳賀:そう。網を曳くようにいろいろ出てきてネットワークが拡がってゆきます。
きた:実は私もバレエ・リュスに興味を持ったのはダンスからではなくて、マン・レイからだったんです。もともと写真が好きだったので。あとはワツラフ・ニジンスキーというスーパーヒーローがいたので、彼はバレエリュスへの最初のとっかかりになりました。そうそう。思い出して今日持って来たんですが、私がバレエ・リュスを知る上で大きかったのが、この展覧会( 舞台芸術の世界ーディアギレフのロシアバレエと舞台デザイン展)です。それまでに単独で見ていたものがこれでつながった気がしました。
芳賀:それはすごく嬉しいです。この展覧会では、本当はやりたかったことが色々制約があってできなかったこともあって、心残りが多々あるんです。でもそれがどこかで実を結んでいると思うと…。

◆ 『結婚』の魅力と難しさ
きた:まずビデオで見た時の絵がとても印象に残ったんですね。構成というか人物の配置が。
芳賀:主役はいるんだけれども、構成上の中央がないという点で、とても現代的ですよね。考え過ぎかもしれませんが、スターシステムへの反旗といったことも考えてしまいますね。
きた:そう、そこなんですよ。あんなに主役が踊ってない作品、ないですよね。あれは群舞の作品に他ならない。
芳賀:逆に言えばリスクが大きくて、群舞の全員が作品を理解して踊らないと成立しない。そこが難しさです。
きた:わかります。マリインスキー・バレエ団が2008年に踊ったのをYouTubeで見たけれど・・・。からだが緩いんですよ。『結婚』はもう少し緊張がないといけない作品のはずなのに。やはり音のとり方が難しいんでしょうね—私も学生時代に諦めた理由は音楽だったんですが—、慣れていないというか、音が始まってから動いちゃうというか、見ていてぶれるんです。
芳賀:確かにあの曲は歌詞もテンポもとり辛い。それと「ビザンチン様式を見せるために」とブロニスラワ・ニジンスカは考えたそうですが、縦のラインをぴしっと出すために、ポワントをもの凄く強く立てなければならない。大変なんですよ。実は私も、6月に久々の再演があるのでロンドンまで観に行ってきたんですが、それもなかなか厳しい仕上がりでした。今回、常連の方が多い席で見たのですが、何回か見ている方だと三本立ての三幕目の前につまらないと帰っちゃうほど。私はそれのためだけにロンドンに観に行っているので悔しいから、「もしかしたら今日のキャストは」って毎日祈るような気持ちで見るんですが・・・。唯一、平野亮一さんって今いらっしゃる日本の方が、今まで特に注目してきたダンサーではないのですが、今回作品の中で自分がやるべき役割を考えて踊っているように見受けられて、感心しました。でも全体では、形もできて音もとれて、でも本当にそれだけ。なまじフォーメーションが面白いし、横にきちっと並ぶのも大変だというので、そこに力を入れすぎて、マス・ゲームになってしまったという感じすらして残念でした。コアがなくなってしまっていたんです。
きた:そうか、その危険性があるんですね。
芳賀:先ほどもお話に出ましたが、英国ロイヤル・バレエ団はニジンスカが再振付をした時のノーテーションを持っているので、フォーメーションは完璧にオリジナル。だからかもしれませんがそれを再現することに血道を上げすぎたのではないかと思います。作品の本質に全く触れてこない。バレエ・リュスの『春の祭典』などを手掛けていらっしゃるミリセント・ホドソンさんと現地でお話ししたのですが、「ニジンスカの作品では、全員が主役で、全員で抽象なのよ。簡単ではないけれど、それをダンサーにしっかり伝えて理解してもらう必要があるのよね」というお話になりまして、実はそこがニジンスカとニジンスキーの作品で通底するコアなのではないかと思うんです。
きた:なるほど。兄妹でつながってくるところがありますよね。昨日見直していて、改めて似ていると思いました。
芳賀:ニジンスキーの継承者はニジンスカしかいなかったと言われる所以ですね。やはり振付の経過も立ち合って相当見ていますし、共に振付けたとも言える『牧神の午後』の、大きいニンフ役は彼女が初演で踊るはずでしたし。『結婚』だって、1914年から始まった作品で、ニジンスキーが振付けた可能性もあるわけです。作曲が長引く間にバレエ・リュスを追放されたニジンスキーの仕事を結果的に妹が受け継いだというのもドラマチックとも、運命的とも言えるかもしれませんね。
◆ もしニジンスカが男だったら?
きた:あの時彼女はまだ30代前半ですよね。それに当時は女性の振付家って珍しくなかったんでしょうか。
芳賀:セルジュ・ディアギレフは、ニジンスカの才能はすごく買っていて、「あなたが男だったら良かったのに」と言ったとも伝えられているんですよ。もう一つ有名な言葉で、「換えのダンサーなんかいくらでもいる。でもニジンスキーの代わりはいない」というのがありますが、やはり天才がそれほど簡単に出ないということを、彼は痛いほどわかっていたんでしょうね。だからその天才の血を引くニジンスカに期待があったでしょうし、実際出来上がった作品が面白かった。それにニジンスキーがやろうとしていたことを推し進めているともかぎ取ったのではないでしょうか。
きた:その後のニジンスカの振付作品、例えば『牝鹿』『青列車』はまた別の作風になってゆきますよね。
芳賀:『青列車』は当時の最先端の避暑地ドーヴィルが舞台で、アントン・ドーリンならではのアクロバティックな要素を入れたバレエという点からスタートした作品で台本がジャン・コクトー、衣裳はココ・シャネル、美術はアンリ・ローランスですし、『牝鹿』はディアギレフの「現在の『レ・シルフィード』を作ってくれ」という、つまり、ストーリーのない情景バレエという発想が元になっているんです。ローランサンが初めて舞台美術と衣裳を手掛けたことでも重要ですけれど…。
きた:時代の最先端。
芳賀:そう。おしゃれなサロン文化の、恋には至らない男女の戯れなどが描かれていますよね。『レ・シルフィード』が森の中の妖精だとしたら、『牝鹿』ではサロンの妖精を切り取っているということになりますね。都市の文化、それも上流階級ばかりとも言えますが、それが当時のバレエ、そしてディアギレフを取り巻いていたの事実ですね。
きた:美術家やデザイナーなど、ディアギレフは結構女性を起用していますね。これからは女性の時代だと?
芳賀:ある程度はね。「好きじゃないけど彼女らの時代だな」と認めざるを得ないというか(笑)。翻って考えれば、ニジンスキーや他の男性ダンサーのようにディアギレフに縛られずにすんだという点で、ニジンスカは才能を自由に発揮することができたと言えるかも知れませんね。実際、彼女はあの時代にフリーランスでいろんな団を渡り歩いていますし、自分のカンパニーを持ったこともありましたし、イダ・ルビンシュタイン一座の振付家だったこともあったんです。忘れられがちですが、『ボレロ』初演時の振付はルビンシュタインから委託されたニジンスカなんです。振付は残念ながら残っていませんが、プログラムをはじめとする資料からは、初演でも丸テーブルが使われていることなどがわかっています。
きた:じゃあ、モーリス・ベジャールの発明じゃないんですね。
芳賀:ないんです。初演はもっとスペイン風の衣装で…。再現は、2009年にシャンゼリゼでそう銘打ったものはありましたけど、何に基づいてどう再現したかがちょっとよくわかりません。ところで女性という点に注目すれば、ニジンスカは確かにバレエ・リュス唯一の女性の振付家なんですけれど、女性性みたいなものは、あまり振付から感じないことはないですか? 私は彼女の作品を見て、むしろ性のなさ、あるいは性を越えてしまっていると受けとめているんですけれど。
きた:確かに、私がニジンスキーやニジンスカの振付を見たときに何を魅力に感じると考えると、体を物体化しているところなんですよね。他の振付を見ると、気持ちというか・・・
芳賀:エモーションをぶつける踊りが時代的にも多い中、彼ら兄妹にはそれがない。
きた:そう。あの時代の表現欲求たっぷりの振付のことや、マース・カニングハムのような見方が後から出てきたことを考えると、かなり時代を先取りしていたんじゃないかなと。
芳賀:ニジンスキーもそうですが、彼女もバレエを内側から壊しかねないことを、言葉ではなくてやってしまっているんですよね。

◆音楽の力と詞の力
芳賀:アンジョラン・プレルジョカージュの、花嫁の人形をぶんぶん振り回す場面のある映像を見たことがありますが、きたさんがおやりになるのはあんな感じじゃないんでしょう? インパクトは強いけれども。
きた:だめなんですよ。ああいう派手で激しいことを、『結婚』の音楽でやることには抵抗がありますね。そういえば、オペラの人の『結婚』の解釈で、「第一部の花嫁がお嫁に行きたくない云々は演技だ」というのを読んで、そこは面白いなと思っています。
芳賀:当時は結婚と言えば、当然そういった処女性の問題などは出てきますね。喜んでいるとそこを疑われてしまうという駆け引きはあるでしょうね。個々の歌詞も、どちらにもとれるものがありますし、登場人物像もあまりクリアではないですよね。また、結婚というテーマについても、両義的どころか多面的な本質を描いてしまっている。今も昔も変わらないなぁと思うのは、例えば男は結婚前の一騒ぎとか。
きた:そうそう。お母さんが悲しんだりとか、今だってそのままですよね。
芳賀:「お嫁にやる」という感覚。最後にドアがパタンと閉まると、完全に別世界に旅だってしまって、その先は闇なんだか何なんだかわからない。
きた:歌詞にしか出てこないけど、「ベッドを温める」っていう表現がありますよね。
芳賀:そこは、例えばローラン・プティだったらもろベッドを出しちゃうとかね(笑)。
きた:出しそう! あれだけシンプルなもので。でもそれもいいと思います。歌詞を無視していないじゃないですか。それ以降の解釈って歌詞を無視しているものが多い気がして、私はそうしたくないんです。
芳賀:聞かないでいられるんですよね。ロシア語だから「音」にしてしまうことができる。あれが英語やフランス語だったら、その後に生まれた作品の方向性は違ってきただろうと思いますね。無視するわけにはいきませんから。この間のロイヤル・バレエにしたって、もし歌詞が英語だったら聞かないわけにはいかないから、違っていたでしょうね。
きた:私もそこで悩まされています。解釈のこともですが、まず「今どこを歌っている?」というところから始まって、歌詞カードと首っ引きで、漸く「はい今両親が来た」「今、新郎の独白」って、わかってきましたけれど。その上で、解釈がどちらにでもとれるところなどは、あまり簡単にしたくないですね。
あと、作曲家のイーゴリ・ストラヴィンスキーが、「『結婚』の初演に満足しなかった」と言っていたということを、聞いたことがあるのですが、ニジンスカ振付の『結婚』の何がダメだったのでしょうか?
芳賀:一つわかっているのは、ストラヴィンスキーは、どちらかというと最初にナタリア・ゴンチャロワが考えていたようなデザインを望んでいたようなんです。彼女は赤に緑に黄色にと、目に鮮やかなロシアのフォークロア調のデザインが得意な人で、最初のデザインではそれが生きていた。でも自分でも考え直し、ディアギレフの意見もあって、白とこげ茶のシンプルな衣裳に背景もシンプルな配色という彼女としてはとても珍しいと言える色彩に落ち着いたんです。
きた:もっとごちゃごちゃしていたほうが良かったんですね。
芳賀:華やかでね。だからストラヴィンスキーの考えていた『結婚』は、あのイメージではなく、元々民謡を採集してそれを元にしていることもあり、フォークロアに根付いたイメージだったのかも知れませんね。今回、衣装はどうされるんですか?
きた:シンプルなものでゆきたいとは考えています。ウェディング・ドレス? んー日本人に似合わないですからねえ・・・。
芳賀:立ち方なんですよ。なぜ衣装を聞いたかというと、あの舞台では衣装や舞台美術の色に意味が与えられていて、大地と空の色とか、心理的なニュアンスを与えられていたりして、見ていて納得するところがあるんです。
きた:なるほど。衣装や道具立てについても安易にしたくはないと思いますが、まずは体の使い方ですね。それを集まってくれたメンバーをどう引き上げて、どう見せてゆくかということをきちんとやらないと。
◆ 群舞の力を上げてゆく
きた:先ほども話題になりましたが、私も主役のいないところが好きなんです。なので今回も、群舞でいいものをやりたいっていう部分が大きいです。
芳賀:一番難しいことですよね。
きた:そうなんです。誰かに頼るとシーンができちゃうし、集団で上に行くって本当に難しい。
芳賀:モチベーションの問題もあるし、みなさんの理解力と、みなさんの身体能力がそろってできること。そもそも日本のコンテンポラリー・ダンスではダンサーは他の作品を踊る機会が少ないですね。そもそもそういう発想がないというか。例えばTOYOTA CHOREOGRAPHIE AWARDの審査員をさせていただいた時に、コレオグラファーが自分で踊るのもありなのか、このコレオグラフィーを他のダンサーに与えても通用するという作品性で評価するのか、つまりコレオグラフィーの賞の基準を問うたら、私は信じがたいと感じたんですが、それがはっきりしていなかったんですよ。
きた:日本の場合、作品というか振付=踊ることが作品となってしまう。振付=踊ること以外に、作品性という枠の評価基準が曖昧な気がします。
芳賀:結局、全部溶け合っちゃっているんですよね。そもそも振付家が自分の作品を他のカンパニーに振り移しすることが極めて少ないという事情もありますよね。コンテンポラリー・ダンスではそれが当たり前で。
きた:一昨年、外部の振付家の再演を目的とした公演を企画をしたことがあって、KIKIKIKIKIKIのダンサー二人で、モノクローム・サーカスさんと北村成美さんのソロ作品を踊るという。作品として良ければ、別の人が踊っても魅力的なはずと思って。
芳賀:それは面白い。北村さんの踊りが他の方に振り移しされるなんて、想像がつかない企画ですね。いかがでしたか。
きた:クリエイションは大変でしたが、作品の魅力ももちろん再確認したし、KIKIKIKIKIKIのダンサーもすごく成長したと思います。その企画『KIKIKIKIKIKI作品委託公演』が北村さんが自分のソロを人に渡すことを初めてした公演だったそうですが、実は今年もArt Theater dBで、『Revival北村成美』という過去の彼女のソロ作品を踊る企画があって、私もダンサーとして参加させてもらいました。人に自身のソロダンスを渡す中で、北村さんも作品を見直したり、再発見したりというプロセスがあったということは言ってましたね。

◆ 作品との距離、制約と自由
芳賀:振りはニジンスカにインスピレーションを受けているのですか。
きた:すでに強烈な印象を受けているので、真似をしちゃいけないと思って、振付を作る間はなるべく見ないようにしました。「私はこの音楽と歌詞と関わるんだ」って。でも昨日、フォルムが被るところを見つけてしまいました(笑)。
芳賀:いくつか変え難いフォルムはあるでしょうね。
きた:そうなんです。アイホールの一作目『生まれてはみたものの』の下敷きにした小津安二郎もそうですが、『結婚』も自分がリスペクトしてやまないアーティストの作品で、もちろん歴史的な傑作。原作に対する距離をどうとるのか悩むところなんですが・・・、でも、私の振付であの身体性を再現したいんですよ。緊張していて、ずっと力を入れていて、全く解放のない動きなんですね。あの状態で踊りを作りたいなというのがまずあります。
芳賀:『春の祭典』の時に、リズムがとりにくい、不慣れな体の動きということで、バレエのダンサーにはなかなか覚えにくいらしいんです。おそらく『結婚』でも同じことが起こっただろうと思うんですよね。全く解放がないとおっしゃったように、そして同時にバレエのパもかなりきついので、踊り手の身体にとってはかなりの制約になると思います。
きた:私は様式美が好きなんです。先日も、伊丹の『まちなか劇場』で相撲を扱ったダンスを振付したんです。太った男の子たちを集めて。そのクリエイションの中で大相撲のことを調べ直してる間わかってきたのが、いろいろ決められている中でどうするか、つまり制約された中での自由に惹かれるということでした。よく「ダンスって自由になれるから好き」と言われますけれど、「自由になることって楽しいか?」と思うんですよね。
芳賀:わかります。私は様式美しか愛せないところががあるかもしれない。本当に自由ということを言い出すと、とても辛いと思う。何も制約のないところに人間を置いたらおかしくなってしまうのではないでしょうか。
きた:何をやってもいいのであれば、その先は破綻するしかないじゃないですか。抑圧する状況がある中で自分がどうするかに興味があるんです。それは一律に義務教育で規則がある日本に特有の考え方なのかも知れないけれど。
芳賀:欧州も同じだと思いますよ。むしろ日本のほうが社会的な制約は少ないんじゃないかとさえ思います。少し話はとびますが、今、外国人がコスプレなどにはまるのは、自分が所属している階層と社会にふさわしい格好以外は実は認められないっていうことと関係しているようなんです。あちらでは、不文律の階層やその場による服装の縛りが実は厳しいですよね。お金があるからと言ってオートクチュールに手を出すということはやはりできない。日本人はその文化と違うところに居るからでしょうけれどそうしたことはあまり意識しないでできるし、その他の社会的な線引きもあまり意識していないわけですよね。モダンダンスで口にされた「自由」だって、ヨーロッパではバレエからの解放ということが明らかだったわけで、今も規範としてのバレエが常に健在です。日本ではどちらも一緒に入って来てしまったので、そのあたりははっきりしませんね。もともとが何からの自由なのかがわからないままスタートしている日本のダンスは、難しいところに来ていると思います。
きた:コンテンポラリー・ダンスという言葉自体、言われ始めた頃の意味を失っているわけですよね。こんなもんだという風に知られてしまって、モダンダンスのように古典化するのか、次へゆくにはまた「ポスト」をつけなきゃならないのかとか。そいうことを考えたときに、昔のダンスに目を向けてみると、例えばバレエ・リュスってすごくアクチュアル。
芳賀:まさに”コンテンポラリー”として登場しましたからね。
きた:古典になったものはすべてその時代を引っ張っていたんだなと考えると、なぜこの作品ができたんだろうということを考える。例えば『結婚』はストラヴィンスキーの曲があって、当時のコンテンポラリーとしてああいう振付、舞台になった。現代でもそれは可能だと思うわけです。
芳賀:できると思いますよ。ストラヴィンスキーに限らず、チャイコフスキーでも他の残っているスコアを現代のものとして読むことは。私は、コンテンポラリーの方が、ストラヴィンスキーに限らず、ですがバレエ音楽を作品に取り込むのを怖がっているところがあると思うので、とても勇気があるなと思いますし、嬉しくもあります。いっそ、グラン・バレエにも挑戦いただきたいくらい。
きた:それで言えば私は、『春の祭典』ばかりがあんなに取り上げられるのかは不思議ですけれどね。歌がないからまだ自由だと思うのかも知れません。ただ、演劇ではチェーホフ、シェイクスピアをいまだにできるわけですよね。ダンスでも、実は素晴らしい舞踊音楽がたくさんある。例えば今年、私は『娘道成寺』を長唄でやったんですよ。やってみて改めて良さを再確認しました。古典だからと前もって構えていたことを軽く越える。舞踊音楽の良さは、ストーリーを作ってくれるところにありますよね。その軸が音楽に存在しているってすごいなと。
芳賀:その軸が、きたさんが今使おうとしている規制、枠なのかも知れないですね。自由になるための。
きた:そう思いました。それで改めてストラヴィンスキーに向かうと、リズムがねえ・・・。
(9月2日@京都芸術センター)
きたまり(きた・まり)
撮影:相模友士朗 1983 年生まれ。2003 年よりダンスカンパ ニ ー「 K I K I K I K I K I K I 」を 主 宰 。以 後 、演 出 ・ 振付・ダンサーとして作品を手がける。 こ れ ま で に「TOYOTA CHOREOGRAPHY AWARD 2008」にて振付作品『サカリバ 007』でオーディエンス賞受賞。「横浜ソロ + ディオ〈Competition〉+」にてソロダンス『女生徒』で未来にはばたく横浜賞受賞。 身体のもつ面白さを幅広い層に提案する ために、作品上演だけでなく、プロデュー ス公演やイベントも多数企画している。
芳賀直子(はが・なおこ/舞踊研究家)
Photo: Nobuyuki Ando 明治大学大学院文学部文学科演劇学専攻博士課程前期終了(文学修士号)。専門はバレエ・リュス、バレエ・スエドワ研究。大学在学時には「近代舞踊史研究会」を運営。幼い頃からバレエに関心を持ち続け、大学で本格的にバレエ研究を開始。研究家として国内外の公演を多数鑑賞、新聞、雑誌、公演プログラムなど各種媒体への執筆や、展覧会監修・企画を実施。各地に招かれての講演など、そのエレガントな語り口による講演の人気も高い。薄井憲二バレエ・コレクション キュレーター。著書:『ICON~伝説のバレエ・ダンサー、ニジンスキー妖像~』(講談社)、『バレエ・リュス~その魅力のすべて』(国書刊行会)、『拍手しすぎる日本人、行列してまで食べないフランス人』(講談社+α新書)
-
- ■2015.7.9
【暑い夏15】C-1「チョンさん突撃インタビュー!... - 2015年度暑い夏(京都国際ダンスワークショップフェスティバル)でドキュメント・スタッフをはじめて担当したあっちゃん&こいちゃ........
- ■2015.7.9
-
- ■2015.7.9
【暑い夏15】 C-1「チョンさん突撃インタビュー... - 撮影:すやまあつし 京都芸術センターに、雨に濡れながらも笑顔で現れたチョンさん。 あぁ、この笑顔。僕がインタビューしたいなと........
- ■2015.7.9
-
- ■2015.7.1
【暑い夏15】 all「ダンスとは」インタビュー... - 私は言い方によっては、「運動をすることを拒否して生きてきた」。例えば「自転車で冒険にいこう」と言われれば嬉々として出かけるが、........
- ■2015.7.1
-
- ■2015.6.13
関典子×白河直子(H・アール・カオス)ダイアログ ... - ダンス・アーカイヴは、一部の舞踊研究者やクラシック・ダンスマニアの関心事と思われがちだが、じつはコンテンポラリー・ダンスのシー........
- ■2015.6.13
-
- ■2014.8.5
【暑い夏14】A-1・2「新しい風を取り入れたい…... - ここ数年、私はフェスティバル会場で出会った方とのご縁をもとにインタビューしていく「わらしべ長者インタビュー」ということを続けて........
- ■2014.8.5
-
- ■2013.9.29
伴戸千雅子インタビュー>ryotaro[UrBAN... - ダンスのうちそと 京都のアンダーグラウンドシーンを支えるライブハウスUrBANGUILD。音楽だけでなく、ダンス、パフォーマ........
- ■2013.9.29
-
- ■2013.6.18
【暑い夏13】一問多答インタビュー ... - インタビュアー・構成:森下瑶 翻訳:橋本純 皆さんは、空間と身体の関係について意識した事はありますか?おそらく普通の........
- ■2013.6.18
-
- ■2013.6.5
【暑い夏13】わらしべ長者インタビュー(2)... - このインタビューのおおもとの動機は、ダンスへの現在形の関心を、体験レポート以外のやり方でも拾い上げることにあります。基本の質問........
- ■2013.6.5
-
- ■2013.6.3
【暑い夏13】わらしべ長者インタビュー《延長編》 ... - 菅井一輝さんは、本フェスティバルから躍進したダンサーを多く輩出する名古屋のダンスカンパニー、afterimage(アフターイマ........
- ■2013.6.3
-
- ■2013.5.27
【暑い夏13】わらしべ長者インタビュー(1)... - 2年ほど前に偶然はじまった「わらしべ長者インタビュー」。これは、会場内でご縁のあった方に声をかけ、このワークショップフェスティ........
- ■2013.5.27

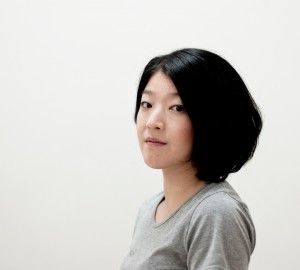






![伴戸千雅子インタビュー>ryotaro[UrBANGUILD]](https://danceplusmag.com/manage/wp-content/uploads/2013/09/004.jpg)



