interview
/home/accom/danceplusmag.com/public_html/manage/wp-content/themes/ac_temp_2/content-single.php on line 23
">
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on bool in /home/accom/danceplusmag.com/public_html/manage/wp-content/themes/ac_temp_2/content-single.php on line 23
大橋可也『深淵の明晰』最終公演前インタビュー
2009年11月1日
 パフォーマンスを通して、現代における身体の在りかたを問い続ける大橋可也&ダンサーズ。これまで関西で上演された、東野祥子への振付作品『9(nine)』(2007年@びわ湖ダンスフェスティバル)、『ダウンワードスパイラル』(2008年@アトリエ劇研)、そして9月の京都芸術センター舞台芸術賞ノミネート作品『深淵の明晰』では、人の身体を見るというパフォーマンスの根本的な関係を強く意識させる演出、閉塞感をまとわりつかせた身体像とそれを切り裂くようなアクションを強く印象づけた。その特異な表現の出所は? 明晰シリーズ三部作の第三作『深淵の明晰』の最終公演を控え、公演地である伊丹のアイホールでワークショップを行った振付家、大橋可也氏にお話をうかがった。
パフォーマンスを通して、現代における身体の在りかたを問い続ける大橋可也&ダンサーズ。これまで関西で上演された、東野祥子への振付作品『9(nine)』(2007年@びわ湖ダンスフェスティバル)、『ダウンワードスパイラル』(2008年@アトリエ劇研)、そして9月の京都芸術センター舞台芸術賞ノミネート作品『深淵の明晰』では、人の身体を見るというパフォーマンスの根本的な関係を強く意識させる演出、閉塞感をまとわりつかせた身体像とそれを切り裂くようなアクションを強く印象づけた。その特異な表現の出所は? 明晰シリーズ三部作の第三作『深淵の明晰』の最終公演を控え、公演地である伊丹のアイホールでワークショップを行った振付家、大橋可也氏にお話をうかがった。 写真提供:AI・HALL
構成:古後奈緒子
『深淵の明晰』公演情報
日時:2009年11月22日(日)18:30開場 19:00開演
2009年11月23日(月・祝)13:30開場 14:00開演
場所:兵庫『伊丹アイホール』
URL:大橋可也&ダンサーズ
『深淵の明晰』画像+映像
身 体 の 向 う に 見 え る も の+ 今日のウォーミングアップの際、参加者に自己紹介を兼ねてワークを出してもらいましたね。フライヤー掲載の鼎談でカンパニーの稽古のことを読んで、「いきなり匍匐前進*だったらどうしよう」と思っていたのですが(笑)。大橋さんがアシュタンガ・ヨガを出されたのは、ちょっと意外でした。
大橋:通常の稽古では、特に決められた動きの型を使ってはいないのですが、アシュタンガ・ヨガはプロセスがはっきりしているので取り入れています。
+ ヨガの流行った社会的背景にも触れられました。身体技術を見るとき、どんな人たちに受け入れられたかといったことも考えるんですか?
大橋:ヨガについての知識は後づけですが、特に作品を作る際、単純に動きそのものというよりは、その背景に何があるのかは気になりますね。例えばヨガブームのように、ある時代や地域や支持層が見えれば、自ずと社会情勢なんかにも広がってゆきます。
+ 伝統的なメソッドだと、身体は天と地のメディアということで、人間を超えた存在へと関心が向かう人もいますよね。
大橋:ヨガはもともと宗教的な精神性に近いものだと思いますが、近代になってフィジカルな部分が切り出されたところが、西洋で受け入れられた要因ではあるんでしょうね。ヨガに限らず身体を見る時、メディア性という部分には関心がありますが、何を媒介するかというところでは、僕は精神的な方向ではなく現実の人に向かいますね。

動 く と 動 か さ れ る の 間+ ワークショップでは、日常の意識の流れをたどるといった考えと、パフォーマーが代わるがわるペアの関係で動きを出し合うやり方を示されましたね。ふだんの作品作りも基本的には同じなんですか?
大橋:始まりはだいたいそうですね。僕はあらかじめこうしたいということがあって、それに従って作っているわけではなく、手探りする状態から始めるので。
+ 9月の『深淵の明晰』京都公演では「動かされる」といった運動モチーフがメインでした。一般に舞台で目にするのは能動的な行為や動作がほとんどですが、大橋さんは、なぜ受動的な身体にフォーカスしようと?
大橋:そこは作家としてのこだわりのようなものかと思います。まず思っているのは、「そもそも能動的な身体なんてあるのか?」「自由とは?」という疑問ですね。僕たちは自由に振る舞っているようだけれど、それは何らかの選択肢がすでにある中でそれを選ばされているわけです。今「動き」と言いましたが、「行動様式」と言ったほうが適切かも知れません。行動様式は外部から与えられるものだと思います。そのあたりに最近関心があるので、舞台上で能動的に動くということが、僕にとって「リアル」ではないんでしょうね。
+ ペアワークで動きを展開していくと、どちらが動かされているのか、わからなくなってしまう時がありますね。
大橋:そこは踏み込んでゆくと、面白いポイントですね。立ちどまると際限なく広がってゆく問題ですが。
見 る 人 が 埋 め て ゆ く 隙 間+ 日常的な動作・行為から作業を進める中で、「ダンスっぽくなってきたと思ったら、少しずらす」と言われました。大橋さんが「ダンスっぽい」と思われるのはどんな時ですか?
大橋:形や様式の問題ではなく、踊っているとか演じているという行為からはできるだけ遠ざかりたいんですよね。ダンスに限らず特定の身体技法があって、それをやること自体が目的になってしまっているようなことは、避けたいと思ってしまうんです。むしろ主体の在りかに絡んでいるかも知れません。そこで行われていることの主体が、ダンサーだったりパフォーマーだったり、個人の人格に収まってしまわないようにしたいなと。しかし、そう考えた時に、先日の「舞台芸術賞」の公開選評会**でも思ったのですが、パフォーマンスの主体が振付家である僕に帰せられる危険性はまだあるなぁ、と思います。
+ 見ている人の中で起こる運動を止めてしまうようなことでしょうか。確かに鑑賞中は、反復の中で演じ手の体が刻々と変化するのを目にして、何に動かされているのか、何とつながってゆくのかと想像できて面白かった。でも、すべては演出家の眼差しを通したもので、パフォーマーは振付家の指示で動いているのだから、最終的に、大橋さんは何を見ているのだろう? 何を見せたいのだろう? とも考えてしまいました。
大橋:もちろん、パフォーマーとは、僕が作る作品という了解の上で、最終的には僕が見たい、見せたい世界を作っているという関係ではあります。ただ、作品作りの途上では、僕から出てきていない要素を多層的に重ねてゆきます。重要だと思っているのは、観客の側がそれぞれの思いが流し込めるように隙間を作っていくことですね。その隙間を通じて、観客自らができるだけ考えられるように、そしてこちらからは答えのようなものはできるだけ出さないようにと考えています。
+ なるほど。見る側のことをかなり意識させられたので、「何か見せてよ」といった姿勢からは引きはがされました。ただ、実験的な作品に対して観客は、作品の主体としての作者の意図を読むことに、かなり強く方向づけられているのでは? その構えは「僕は答えを示しません」と言われても、結構頑固でひっくり返らない。
大橋:お客さんの一般な構えとしては当然だと思いますし、そのことを踏まえた演出的な仕掛けは作品ごとに考えますね。一つの試みがすべてのお客さんに対して十全であり得るとは思いませんが、見る人が入り込める手がかりを準備して、作品に入り込んでもらった上で、自分にしか見えないものに集中してもらうように持ってゆきたいとは思っています。ただ、言葉との関係については、先の公開選評会で貰ったコメントと絡めて、ちょっと思うところがありました。そのコメントは、パンフレットに書いた「グローバリゼーション」という言葉を拠り所にしていたんですが、パフォーマンスとは別のところで形成された大きな価値観があると、どうしてもそこに寄りかかって見てしまうんだなぁ、と。それは誰にでもあることですが、そのせいで想像力を限定してしまうことは、僕は避けたいほう。だから観客を引き込みつつその能動性を引き出しつつということに関しては、その都度塩梅を変えていますね。

パ フ ォ ー マ ン ス か ら 体 と 向 き 合 う こ と へ+ 大橋さんは、体について、いつ頃意識されました?
大橋:僕の場合は、もとから体ということを意識していたわけではなく、パフォーマンスを提示したいと思った時に、体に目がいったんだと思います。きっかけは、1991年にワーキングホリデーでバンクーバーに滞在していた時、参加したパフォーマンスの集中ワークショップでした。そもそもなぜカナダに行ったのかというと、生きていて特にやりたいことがなく、何もすることがないので、「海外にでも行ったら自分の生き方が変わるかな」と(笑)。もちろん環境が変わったからといって、本人が変わるわけじゃない。つまらない悶々とした日々を送っていたんですよ。そこで、たまたま手にしたフリーペーパーでワークショップの広告を目にして、暇だから行ってみた。そこはダンスだけでなくヴォイスも使いましたし、今思うとコンタクト・インプロヴィゼーションが入っていたり、舞踏にインスパイアされたムーブメントもありました。そのワークショップの最後の日に参加者が作ったものを発表したんですけれど、その時「あぁ、これは面白い」と。何が面白かったのかと考えてみると、人との関係性だったんですね。その時からずっとなんですけれど、僕にとってパフォーマンスとは、人との関係性を新たに構築することだと思います。それは観客に対してもそうですし、作品作りの過程でのスタッフ、ダンサーとの関係なんかも。また、劇場外でも、自分がパフォーマンスをやっているということから生まれる関係性がある。僕がやりたいのはそういったことだと。そんな風に気づいた時、受けたのがダンスを取り入れたトレーニングだったということもあってか、まずは体というものと向き合わなくてはいけないのかな、と思ったんです。
+ 関係性を開く基盤が体だと?
大橋:そこはまだ直接つながっていなかったと思います。実は、パフォーマンスというものに出会うまでは、体というものがすごく邪魔な存在だったんですよ。なんで自分にはこんな体があるんだろう? 何でご飯食べて、トイレに行って、寝なきゃいけないんだろう? そういうことがすごく自分にとって不必要なものだという風に思っていたんです。たぶん中学生、ひょっとすると小学生ぐらいから、自分はこの体に縛り付けられているという感覚をずっと持っていた気がします。
+ パフォーマンスを知ってそのあたりは変わっていったということですが、体に向き合うというのは具体的にどのように?
大橋:バンクーバーで既に、日本人なので舞踏をやったほうがいいのかなという短絡的な発想と(笑)、もう24歳だしこれからバレエとかモダンっていうのもなっていうのとで、舞踏をやろうと考えていて、帰国してから当時アスベスト館で教えていた和栗由紀夫さんに学ぶようになりました。もちろん、僕が体験した暗黒舞踏には、体をつくる方法も含まれていましたけれど、僕にとっては身体訓練というより新たな認識方法を獲得する手段なのだと思っています。踊りを作る過程での、ものの見方、捉え方を学んだところですね。身体訓練についていえば、同時期に自衛隊にも入っていたので、そちらでの体験も貴重でした。僕がいたのは特別儀仗隊というかなり特殊な部隊で、具体的には外国の要人が来日したときなんか、ニュースで数秒映ると思うんですけれど、迎賓館などでお出迎えをする役目ですね。行進して、「右へならえ」して、「捧げ筒」をするといったことを、普段は延々練習するんです。まさにヴィジュアル担当ですね(笑)。見せることをかなり意識した訓練なので、とても勉強になったと思うし、身体にもすごく入ってきたなと思います。

時 代 の 違 い を 意 識 す る こ と+ その後、ブランクを経てアシュタンガ・ヨガも取り入れるようになられた。パフォーマーの経験としても特異ですが、作品に出てくる身体像を思い出すと一転して、鍛えられた生き生きした身体ではないですよね。ご自身で「踊らない」ということもおっしゃっていますし、舞踏とも関係しているのかも知れませんが、そういったモダニズムのダンスが提示してきた身体に対するアンチテーゼみたいな意識はあるのでしょうか。
大橋:もちろん、自分の立ち位置は常に意識せざるをえないので周りは見ますけれど、そういった意味での先行世代には特に思い入れはありませんね。ただ、ちょっと質問とはずれますが、全共闘から上の世代では、ダンスに限らず芸術全般が、高尚なこと、大層なことをやっているという意識があるように感じていて、それに対しては、舞台だとか芸術といったものを、もっと身近なものとして見せたいとは思います。
+ 60—70年代の芸術運動は、確かに社会にコミットする思想と強い結びつきを持っていて、その後のノンポリだとか、消費に方向づけられた私の世代と対比されます。ただ、その後、社会的な意識とつながりにくい状況の中で、パフォーマンスが生みだすソーシャルな関係にもとづいて世間と関わり、コミュニケーションのあり方を流動化しようと試みてきた作家は少なくない。にもかかわらず、そのような活動の社会的側面について語ろうとすると、かつての芸術を知る方からはつまらないもののように受けとめられてしまう。
大橋:そこがいやなところですね。学生運動とかもそうなんですけれど、知識層が知識を持たない人に対して、率先して社会変革なり革命なりを起こしてゆくという姿勢を感じて。それに近いものが演劇や芸術の運動にもあるような気がしていて、つまり自分達が先を行っているという意識があるんじゃないか、逆にそういう意識が活動を支えていたんじゃないかって思います。一方で、僕の師匠にあたる和栗由紀夫さんらが足を踏み入れた暗黒舞踏と社会との関係には影響を受けていると思います。どういうことかと言うと、70年代に入り土方巽がアスベスト館に籠って作品を作った時、そこに集まって来た若者達がいたわけですよね。彼らは、何かからあぶれてしまった、行くところがなくて集まってきたんだと思うんですよ。芸術がその求心力になったことには一定の社会的意味合いがあると思っていて、そこで芸術に活かされたのか社会的に更正したのかといったところは僕は評価できないけれど、集まるというモチベーション自体が重要だったと思うし、そのような関係性があったということは羨ましい。そこは何とか別のかたちで乗越えなくちゃいけないんじゃないかと思っています。

劇 場 っ て ど ん な 場 所 ?+ その時代の演劇は、積極的に社会からあぶれて、秩序をはずれた考えや行為を探れる場として力を持てたんですよね。今、「祝祭」や「連帯」という言葉も効かない体を相手に、まずは何がしかの関係を結ぼうと考えると、劇場ってどんな場所なんだろう、どんな人が集まって来ているんだろうって思うんです。祝祭の場であれという考えもあったし、逆に一人になる空間でよいという考えもある。大橋さんは、どう考えますか?
大橋:自分の経験にひきつけて考えると、自分が一人であるということを見いだす場所なのかなとは思います。ただ、実際に僕の作品を見に来てくれるお客さんにとってとなると、ひっくるめて語ることなんてできない。例えばコンテンポラリーダンスのお客さんと被っているとはいえ、正直、そういうシーンを形成しているお客さんというと、よくわからないところがあるんですよ。僕の作品を必要としている人というのは誰なんだろう、何が見たいんだろうっていつも考えていますし、そもそも僕が見て欲しいと思っている人が来ているのかな、そういう人に届けることができているのかなと、ここ数年気に懸っていることではありますね。
+ 作品作りだけでなく、チケットの料金システムにも配慮されていますね***。どんな人に見て欲しいと、大橋さんは思っているんですか?
大橋:それは第一に、僕なんですけれどね(笑)。さきほど話したように、これまで自分にとって体がすごく邪魔なものだと思っていて、パフォーマンスに出会って、体と向き合うようになった。向き合えているかは未だにわからないですけれど、人との関係性を意識するようになった。作品を見る人には、そういうことに気づいて欲しいなと思います。例えば人との関係性に困難を感じている人でも、こういう関係性がある、こういう身体のあり方があるっていうことに気づいてもらえたらいいなって。
+ 私もダンスを知る前はそうでしたけれど(笑)。それは特殊な人だけがそう思うのでもないだろうと思っていて、今の時代に身体が置かれている状況と絡んでいるのではないでしょうか?
大橋:繰り返しになりますけれど、僕にとって身体を語るときは、パフォーマンスをする、つまり関係性を作るということがまずあるんです。だから身体というものを一面的に切り取れるものだとは思っていないんだけど、人や社会といったところの関係性、自分と他者の関係が、決まりきったもの、固定されたもののように、若い人たちが捉えているんじゃないかなあとは思います。会社は会社、家族は家族、自分は自分。特定のジャンルに関心がある人はその領域にしか向かわない。現実にはたくさんの関係があって、それぞれのつながり方はどんどん変わっていったり、動いていったりするのに、そこをただ素通りしてしまっているんじゃないかって。そういった日常の中では、個人の体も一つの意味づけに収まってしまうんじゃないかと。
+ だからこそ、パフォーマンスは関係性ってところに関わる場だということですね。『深淵の明晰』の最終公演に向けて、今どんなことを考えておられますか?
大橋:僕の作品はずっと閉塞感というか、出口のない状況を描写していたと言われてきましたし、実際そうだと思うんですね。今回もそうで、現実の描写だけじゃないかと言われればそうかも知れませんが、その中に少し僕なりに明るい、次につながるものが見えてきたなあと。希望はあるんじゃないかなあと。それは奇しくも今の政治的な、社会的な状況とも重なるのですが、今までの築いてきたものに固執することではなくて、新しい人のあり方やそのつながり方への入り口に立てたんじゃないかなあって思っています。
+ 楽しみにしています。ありがとうございました。
*「創世時代は全然ダンスの稽古らしいことをしなかったんですよ。匍匐前進とか、走っていって壁にぶつかってまた走る、とか。特に匍匐前進はかなりやらされました。」(『深淵の明晰』チラシ「鼎談:大橋可也&ダンサーズ」より)
**大橋可也がノミネートされ、『深淵の明晰』を上演した「京都芸術センター舞台芸術賞2009」の一環で、9月27日に行われた。
***「芸術に関する対価が一般的な「相場」で決まってよいのか、という疑問から、2007年『明晰の鎖』より新しい料金設定を提示し、話題となっている。チケットA20,000円(お金に余裕があるので、作品に貢献したい方向け)とチケットC 0円(お金に余裕がないが、どうしても作品を見る必要がある方向け)は観客に作品に関わる意思表示をしてほしい、という創作者の主張である。」(『深淵の明晰』プレス・リリースより)
(2009年9月18日@アイホール)
大橋可也(おおはし・かくや) photo:GO
大橋可也&ダンサーズ主宰・芸術監督。平日はシステム開発の業務に携わりながら創作活動を続ける。山口県宇部市生まれ、横浜国立大学経営学部卒業、イメージフォーラム付属映像研究所卒業、陸上自衛隊特別儀仗隊出身。1991年、カナダヴァンクーバーにてパフォーマンス活動を始める。1993-1997年、和栗由紀夫に師事、土方巽直系の舞踏振付方法を学ぶ。1999年、大橋可也&ダンサーズを結成。2000年、「バニョレ国際振付賞ヨコハマプラットフォーム」に出場するも、出演者が全裸であるという理由で非公開の審査となる。その後、活動を休止。2003年に活動再開以降、複数のコンペティションに出場するが、いずれも受賞を逃す。2005年、ニューヨークの代表的なアートスペース「The Kitchen」に招聘される。2006年より「明晰」三部作の発表を開始。2008年12月28日に新国立劇場小劇場にて新作『帝国、エアリアル』を発表。「ダンスとは何か」という問いへの探求を通じて、現代における身体の在りかたを提示し続ける作品を作り続けている。
-
- ■2015.7.9
【暑い夏15】C-1「チョンさん突撃インタビュー!... - 2015年度暑い夏(京都国際ダンスワークショップフェスティバル)でドキュメント・スタッフをはじめて担当したあっちゃん&こいちゃ........
- ■2015.7.9
-
- ■2015.7.9
【暑い夏15】 C-1「チョンさん突撃インタビュー... - 撮影:すやまあつし 京都芸術センターに、雨に濡れながらも笑顔で現れたチョンさん。 あぁ、この笑顔。僕がインタビューしたいなと........
- ■2015.7.9
-
- ■2015.7.1
【暑い夏15】 all「ダンスとは」インタビュー... - 私は言い方によっては、「運動をすることを拒否して生きてきた」。例えば「自転車で冒険にいこう」と言われれば嬉々として出かけるが、........
- ■2015.7.1
-
- ■2015.6.13
関典子×白河直子(H・アール・カオス)ダイアログ ... - ダンス・アーカイヴは、一部の舞踊研究者やクラシック・ダンスマニアの関心事と思われがちだが、じつはコンテンポラリー・ダンスのシー........
- ■2015.6.13
-
- ■2014.8.5
【暑い夏14】A-1・2「新しい風を取り入れたい…... - ここ数年、私はフェスティバル会場で出会った方とのご縁をもとにインタビューしていく「わらしべ長者インタビュー」ということを続けて........
- ■2014.8.5
-
- ■2013.9.29
伴戸千雅子インタビュー>ryotaro[UrBAN... - ダンスのうちそと 京都のアンダーグラウンドシーンを支えるライブハウスUrBANGUILD。音楽だけでなく、ダンス、パフォーマ........
- ■2013.9.29
-
- ■2013.6.18
【暑い夏13】一問多答インタビュー ... - インタビュアー・構成:森下瑶 翻訳:橋本純 皆さんは、空間と身体の関係について意識した事はありますか?おそらく普通の........
- ■2013.6.18
-
- ■2013.6.5
【暑い夏13】わらしべ長者インタビュー(2)... - このインタビューのおおもとの動機は、ダンスへの現在形の関心を、体験レポート以外のやり方でも拾い上げることにあります。基本の質問........
- ■2013.6.5
-
- ■2013.6.3
【暑い夏13】わらしべ長者インタビュー《延長編》 ... - 菅井一輝さんは、本フェスティバルから躍進したダンサーを多く輩出する名古屋のダンスカンパニー、afterimage(アフターイマ........
- ■2013.6.3
-
- ■2013.5.27
【暑い夏13】わらしべ長者インタビュー(1)... - 2年ほど前に偶然はじまった「わらしべ長者インタビュー」。これは、会場内でご縁のあった方に声をかけ、このワークショップフェスティ........
- ■2013.5.27

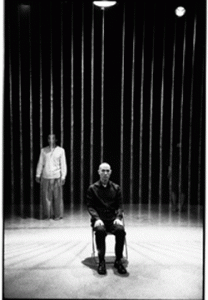





![伴戸千雅子インタビュー>ryotaro[UrBANGUILD]](https://danceplusmag.com/manage/wp-content/uploads/2013/09/004.jpg)



