interview
/home/accom/danceplusmag.com/public_html/manage/wp-content/themes/ac_temp_2/content-single.php on line 23
">
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on bool in /home/accom/danceplusmag.com/public_html/manage/wp-content/themes/ac_temp_2/content-single.php on line 23
セレノグラフィカ 隅地茉歩・阿比留修一『皮から食べて』インタビュー
2009年08月21日
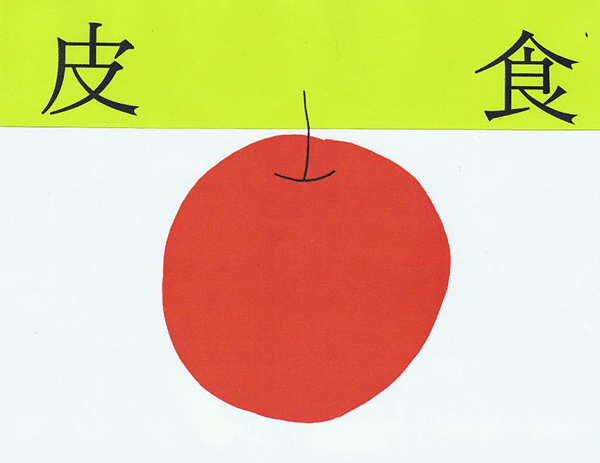
セレノグラフィカ 新プロジェクト『皮から食べて』インタビュー
今年結成12年を迎えたダンスユニットselenographica(セレノグラフィカ)。1997年の結成より、きめ細かい振付にユーモラスな仕掛けで評価を得、2005年にTOYOTA CHOREOGRAPHY AWARD(トヨタコレオグラフィーアワード)を受賞。劇場内外で、創作公演からアウトリーチまで幅広く活動を展開してきた。2004年より、照明家・美術家の岩村原太を技術監督に迎え、西陣ファクトリーGardenで、踊ることと観ること双方の実験的交流の場を作りながら、コンスタントに作品を発表し続けている。観客を心理的、身体的に巻き込み、社交に長けた大人から素朴な子供まで参加できる遊戯空間を生みだすその作風はどのようにもたらされたのか? 結成の経緯から、新作『皮から食べて』での取り組みについてお話いただきました。
構成:古後奈緒子
■ セレノグラフィカの歩み+ちょっぴり時代背景も
日時 2009年8月29日(土)14:00 / 18:30
2009年8月30日(日)14:00場所 西陣ファクトリーGarden
詳細情報はコチラ>>>振付・構成・演出 隅地茉歩 技術演出 岩村原太 出演 阿比留修一、隅地茉歩、花沙、升田学
+ 異なる分野出身のお2人がセレノグラフィカとして活動することになった経緯は?
隅地 今年でもう結成12年になりますが、出会ったのはさらに3年ほど遡って、たまたま一緒に出演することになった、しかもバレエの舞台なんですよ。1994年に、京都市の平安健都1200年と、京都シティーフィル合唱団30周年の記念事業で、 『カルミナ・ブラーナ』という創作バレエの記念公演が催され、私は個人レッスンを受けていたイギリス人の先生が振付をしていた関係で、さらに様々な偶然が重なり群舞の一員として出演することになったんです。
阿比留 僕がその舞台に出演したのもたまたまです。今もそうかと思いますが、バレエの領域は男性ダンサー不足。男女ほぼ同数という珍しい編成の作品だったため、芸能専攻のある大学に男性ダンサー募集が来たんです。当時僕は、近畿大学を卒業して神澤和夫先生に師事していたのですが、そこは男性が多かったこともあって、塊で借り出されたんです。
隅地 それでシーンごとに異なるペアを組むのですが、やはり相性があるんですね。阿比留さんと息が合ったこともあり、公演終了後も連絡をとりあって、お互いの出演する公演を観合ったり、他のいろんなダンス公演を観て廻るようになりました。当時はちょうど、マース・カニングハム、モーリス・ベジャール、リンゼイ・ケンプ、アルビン・エイリー等、海外の有名なカンパニーが立て続けに来日した時期で、山海塾も、私はこの時期に初めて観ました。また、1996年からDANCE BOXも始まり、関西でもインディペンデントリーに活動していた人がすでにたくさんいましたので、立ち上げの1997年前後は、そういった公演を本当によく観に行きました。
+ カンパニーに所属していながら旗揚げを決意されたのは?
隅地 私が所属していたカンパニーに限らないと思いますが、やはり集団には何らかのヒエラルキーに近いものが生まれ、その中での価値観も先生の目にどう写るかに左右されがちです。鍛錬すること自体の充実の一方で、そういうことに次第にズレを感じ始めました。それが『カルミナ・ブラーナ』で、阿比留さんを始め、異なる土壌で稽古を重ねて来たダンサーと共演し、また創作方法という点でも目を開かれる思いをしたんです。さらにいろいろな外部の作品を観るようにもなって、表現の可能性に解放感を覚える一方で、自分で作品をも作ってみたくなってくる。個人的な事情も重なって、私は退団を決意しました。
阿比留 僕はカンパニーでも目をかけて頂いていましたので、先生に隅地さんとの活動の理解を求めながら、独自の活動を探っている状態でした。当時はJCDNのように選抜してプログラムを組んでいるような組織はまだなく、ショウケース的な発表の機会もDANCE BOXと「アルティブヨウフェスティバル」が主でした。なので、年に1回ずつ自主公演の形で本公演をうちながら機会をつなげていったのですが、当時は、多くのカンパニーが他門の人と何かやれる雰囲気ではなく、最終的にはセレノグラフィカを旗揚げしてからしばらくして、元のカンパニーには距離を置くということを決断しなくてはならない状況になりました。
+ コンテンポラリーダンスの走りの頃には、カウンターの意識はなくとも、集団を離れる葛藤や個になるエネルギーがありましたね。
隅地 それはあったと思います。2000年にKAVCの「ダンスフロンティア」という企画で、セレノグラフィカではなく私の振付作品を3本やらせていただいたのですが、その時神澤先生の研究所所属の男性ダンサーをお借りして作った作品がきっかけで、阿比留さんも私も研究所とのお付き合いが叶わなくなってしまいました。いろいろ話し合い、悩みましたね。そうなった時に、責任と言うとかっこ良すぎるかも知れませんが、先生や残って踊っておられるダンサーの人たちにも、何かの拍子で観てもらったときに、少なくとも「こういうことがしたかったのか」と納得してもらえるようなものを作って行かないといけないんだといった気持ちが当初はありました。確かに、そんな風にして何かを踏み切り板として活動を始めるのとそうでないのとでは、エネルギーは違ったと思います。ただ、本当に自分のものだと言える表現が出てくるのは、先生の教えを絶対的なものとして身体の中に入れ、習い、さらっていた経験からの離陸ということが、意識されなくなってからだと思うんですよ。そうなるのにやっぱり数年かかるわけですよね。
■ ターニングポイント/“よい作品”があれば済むことなの?
 + 近作には劇場でのコミュニケーションを縦横に畳んだり広げたりする、実に細かい仕掛けが認められます。いつ頃からこのような手法を取られているのでしょうか。
+ 近作には劇場でのコミュニケーションを縦横に畳んだり広げたりする、実に細かい仕掛けが認められます。いつ頃からこのような手法を取られているのでしょうか。隅地 セレノグラフィカとして積極的に活動を始めると同時に、より広い関係の中で創作をするようになってゆき、その中でそれまで意識しなかったつながりを意識させられることになったんだと思います。まず2001年に「下鴨気象」でじゃれみさ(砂連尾理と寺田みさこ)とデュオ×デュオで公演を打ち、このとき初めて、自分達の身内でないお客さんに観てもらったんじゃないかしら。
阿比留 関西でDANCE BOXとかJCDNとかが動き出しているのは知っていたけれど、プロデューサーにも積極的に観てもらおうとしだしたのもこのあたりですね。本来なら数回参加するのが通常となっている「ダンスサーカス」*という段階をすっとばして、ビデオ資料を手にDANCE BOXのプロデューサーの大谷さんと交渉し、DANCE BOXの最初の拠点、TORII HALLで『樹下の双魚』の本公演を打たせてもらったりしました。*振付家の登竜門的な役割を果たしてきたDANCE BOXのプログラム
隅地 2002年のアルティブヨウフェスティバルにも、初めてセレノグラフィカとして『イシュタルー境界をつなぐものー』という作品を出しましたが、これがきっかけで、DANCE BOXからその年の「踊りに行くぜ!!」に推薦してもらえることになりました。「踊りに行くぜ!!vol.3」に参加したことは大きくて、作風が目に見えて変わりましたね。というのも、『イシュタル』その他のレパートリーで巡回することが望まれず、TORII HALLで上演した本公演『樹下の双魚』の中でJCDNのプロデューサー、佐東さんが覚えていたシーンを元に、作品を作ることになったんです。
阿比留 そのシーンというのが、正座して僕が隅地のお尻を触ったり、どつかれたりしながらじりじりと後ろに下がってゆくという(笑)、僕らにしてみれば鑑賞の箸休めくらいに挿入した部分だったんですね。それまではどちらかというと、シリアスで重厚な、お客さんにとっては注視する以外の逃げ場のないような場面の連続だったので。だから、その場面を指定された時、お客さんを楽しませるということで隅地は抵抗はなかったみたいだけど、当時の僕にしてみれば、ダンスと思ってもいなかった箇所だったので戸惑いましたね。ただ、時間がかかりましたが、上演した時に客席からかえってきた反応から、新たな面白さとともに可能性を感じもし、このあたりの経験は大きなターニングポイントになっています。
隅地 実際に「踊りに行くぜ!!」ではお客さんの反応が良く、自分たちのダンス観を覆されるとともに、縁もゆかりもない土地の見知らぬ人に迎えられる純粋な喜びを知ることもできました。ただ、今度はそこで自分達が得たものの自己模倣に陥ってしまったんですね。その後は苦しみながら、様々に活動を模索しましたね。近年別ダンサーでの再演を行っている『FASNACHT』の初演もこの時期です。が、自分たちの手持ちのボキャブラリーや方法で作品を作ることに限界を感じてもいて、外からもいろいろ吸収したいと考え、2003年秋に劇場照明の勉強会である「光の塾」(岩村原太主宰)に入ったんです。そのことが、原太さんをはじめとする様々なアーティストとのコラボレーションや、西陣ファクトリーGardenという場での研究上演会を始めるきっかけとなりました。
阿比留 「光の塾」で面白かったのは、ダンス以外の創作論理に触れたことでした。それまでは動きの論理だけで作っていたのですが、一度、僕たちが短い踊りに合わせて書いた進行表を、他の参加者が解釈して照明をつけるという試みをしたとき、その解釈のばらつき、論理の違いに愕然としたんですね。そこでダンス主導と違う見方、考え方に触れることができたのは大きかった。それで2004年の夏に作った『それをすると』からは、集まったアーティストに一から作ることに参加してもらい、その中で、原太さんがセレノグラフィカの活動に欠かせない存在となりました。さらに公演の場所も、NHKのケーブルテレビへの出演中に尋ねられて急場で決めたことですが(笑)、彼の運営している西陣ファクトリーGardenに決まりました。この作品は、結果的にTOYOTA CHOREOGRAPHY AWARD2005での受賞作のベースともなり、今でも一番再演が多く、一番たくさんのお客さんに観てもらっている思い出深い作品です。
+ 観客とコラボレーターとの関係から、どのような関心が展開していったのでしょう?
隅地 ダンス以外の方法や論理を持ったアーティストとコラボレーションをすること、とりわけ原太さんに加わってもらうことで、セレノグラフィカはより複眼的になれたと思います。自分で作って自分で踊ると、完全な客観視は難しい。そこにはどうしても生理が生じるので、繰り返して高揚感を得たいということにも、逆に疲れてこれ以上繰り返したくないということにも左右される。だから、その生理の生じない人間の見え方が聞けるというのは有り難いし、踊っている者だけがタイミングを決められるのではないということをまざまざと突きつけられもします。以降は、ミュージシャンでリコーダー奏者の迫田さん、俳優の二口大学さん、contact GonzoでdBスタッフでもある塚原悠也さんと、その都度コラボレートするアーティストを変えて作品作りに取り組んできました。迫田さんとは既成曲を脱した音楽との取り組み、二口さんとは言葉を中心に据えた試みを。TOYOTA CHOREOGRAPHY AWARD2005の受賞公演は、『それをすると』と二口大学さんとの『終わらない段落』とのカップリング公演だったんですよ。
『それをすると』でもう一つ勉強になったのは、西陣ファクトリーGardenから、KAVC、世田谷パブリックシアターへと、異なる場所で再演を重ねた経験です。Gardenとパブリックシアターでは、舞台容量や客席数をとっても数倍ではおさまらないほど違う。その場にとって一番大切なことは何かということ、その劇場なりに再生させる(再現ではなく)ということを強く意識させられましたね。よく喩えるのですが、巻き寿司を海外で作ったとして、例えば千鳥酢がなくてワインビネガーで代用しなければならないetc…といった時のように、何をもって巻き寿司とするのか、その場その場で問われるよなあってことを、話し合いましたね。単にアレンジするだけなら簡単なのですが、何が必要で何が要らないかということを真剣に考えるようになったんですね。その際、空間と一口に言っても、劇場内での物理的条件だけじゃなく、そこがどんな風土で、どんな立地条件で、どういう歴史的背景があるのか、いくらでも細かく考えてゆけますね。また、どういう人が観に来てくれるかを考えるというのは、特に岩村がいつも言うことですね。翻ると、結成以来7年間、作品を作るというときに、そういった空間や場の要素を二の次にしていたということにもなります。今でこそ、観客との相互のやり取りの中で何かが形成されてゆくものだという風に思っていますが、それまでは、自分達がやりたいことをベストの状態で上演することが一番大事なことのように思っていましたから。そのあたりは頑なだったんですね。
阿比留 確かに作品を作ることで終わっていて、人前でそれを踊る、「上演する」ということについてはあまり考えていたなかった。最初はやはり、“いい作品”を作ればわかってもらえるという意識で、それを観に来てもらえさえすればいいという姿勢。作品作りも、自分の中にあるものを外に出す感覚で、観客との相互作用という感触はなかった。だからかえって、『待たない人』あたりでその問題が気になりだしたときに、どんな風に会場に入ってもらって、どんな風に待っていてもらいたいか、会場の雰囲気、終演後持ち帰ってもらいたい感覚など、細かく考えるようになったんでしょうね。
隅地 信念にのっとって、自分の納得するダンスをすれば、みんなは絶対わかってくれるという思い。それは間違ったことではないと思いますが、そう思っていたときは、お客さんという大きな要素が持つ可能性に対しても閉じていたんだと思います。それが公演ごとに、客席に向かって関係を開いてゆき、具体的な手応えも得られた。そのことの延長線上に、昨年は2人だけの『10099101』を制作しました。岩村との共同作業が始まってから初めて、コラボレーションではなくデュエットに戻したのも、一緒に作り上げる関係の重要な相手として、観客が意識されてきたということもあります。もちろんそのこと自体も到達点ではなく、また次の関心を見つけなければいけないと思っていますが、昨年、3つの研究上演を『10099101』へと発展させたことで、変わらず大切にしたいことはこれかなというものは、見つけた気がしますね。それは、時間と空間を人びとと共有するといったこと、そのために試した数々の手段とその手応えと言えるかも知れません。
+ コンテンポラリーダンスの名の下に作られてきたシーンにおいて、作家の多くが、観客との関係や、場作りを意識して身体技術化もしていっていると考えられる半面、観客の側に、表現やその場を支えているのだという意識が薄いような気もしています。それは、“面白い”作品がないといった、単純な話では済まないように思われるのですが。
隅地 言われたような温度の低い状況は、関西だけではないようですね。阿比留が一緒に仕事をした東京の演出家の方も同じような話をしていたと聞きました。作家の仕事はもちろんよい作品を作り、届けることですが、それは必要であっても十分ではないし、「面白い作品がない」というのは、それこそ作り手の側の「いい作品をベストな条件で上演しさえすれば…」という理屈と同じで、出口を持たない議論だとも思います。観客の側に共犯意識のようなものをかき立ててゆかないと、やる側も観る側も貧困になってゆく気がしますね。
阿比留 後、鑑賞の形態自体を考えることにも可能性があると思います。

■ 新プロジェクト『皮から食べて』=セクシーな(?)セレノグラフィカ
+ 今回は、どのような関心で作品作りに入ったのですか。
阿比留 コラボレーションを数年してきて、改めて2人だけのデュエットに戻ったその先に、改めて「やりたいことは?」と考えたとき、単純に複数のダンサーとやりたいとは思っていました。
隅地 そこで誰をと考えると、曖昧な言い方かと思いますが、体に饒舌さと沈黙、両方を持っている人がいい。どちらかを持っている人はたくさんいるような気がするんですけれど、両方は珍しいように思っていて、升田学さんと花沙さんにお願いしたのはそのことが理由です。2人には私たちの旧作レパートリー、『FASNACHT』を振り移しして、何度も踊ってもらっています。中でも維新派で長く活躍してきて、最近自分の劇団を旗揚げしたばかりの升田さんは、いまもアイデンティティのありかは役者だと思うんだけれど、そのことが振付をするにあたってなんの邪魔にもならない。自由度が高いんでしょうかね。
阿比留 2人とも僕より若く、おまけにそれぞれ背景もキャリアも違うけれど、共感している部分というのは、一カ所に留まって何かにこだわった経験と、何かを変えようとする意識の両方があるところかな。升田さんにしても、もともと美術畑だった人が、維新派を観て演劇観が変わり、即入団してその経験を結構長く積んで、今度は自分で旗揚げして何かを作ろうとしている。花沙さんも現代舞踊協会的なところを通過して、今そうは思えないような表現をやっている。今、そういう経験の上で何かをやろうという人たちと一緒に作品を作ることが大事なような気がしています。何にこだわって、何を変えたくてこの身体が出て来たのか。変えようと思っても染み付いてしまっていて、葛藤を抱えたりもするかも知れないし。今回の作業をとおして、これまで見られなかったようなものを、彼らとセレノグラフィカ双方にとって引き出せたらいいなと思います。
隅地 自分たちが男女でやっているということもあり、ずっとこだわってきたデュエットを目の前に据えて観てみたい、男の体と女の体を対象化して見たいということも一つあります。もちろん誰でもいいわけでなくて、先に言ったような質感…体の中に闇のある人がいい。それと、タイトルやチラシで少し匂わせていますが、今まで男女のデュエットでやってきたのに、セレノグラフィカには当たり前の男女のというか…セクシーなところに触れる要素って、なかったんですね。とりたてて避けてきたわけではないけれど、そういう方向には行かなかったし、実際、そう見られることもない。これまで触っていなかったところに、今回は敢えて触りたいというところもあります。2人の身体を対象化して徹底的に(笑)。
+ 7月からのリハーサルを経て、現在佳境に入られたとのこと。どんな振付方法を? その中で何か見えてきたものはありますか?
隅地 4人でユニゾンで踊るような振りは作ってしまって渡したりもしますが、基本は言葉やシチュエーションを渡して、2人に何かをしてもらい、見え方、やり方を決めてゆくといった組み立て方をしています。組み合わせも、2人は2人、私たちは私たちではなく、相手が変わることで出てくる質も違うので、そこも見ながら決めています。
阿比留 そういうやり方は、ダンサー泣かせらしいということも、だんだんわかってきましたね(笑)。面白いのは、我々ダンサーは体を使う専門職なので、すぐダンスコードに入ってしまうんだけど、升田さんはいい意味で、課題として与えられたことに対して、ダンスではない返し方をしてくれる。僕らのやるのは、どこかで観たことあるようなダンスだったりするんだけど、升田さんの表現はダンスの「当たり前」をはずれることで、新鮮というか、振り返っていろいろ気づかせてくれますね。それを他の3人で楽しんでいたりしますよ。
隅地 そうね。花沙と3人でやっていると、自明の前提のようにあるコードに入る、ある出発点をとる。異分子が入ることによって、そこが問い直されるんです。私たちがすんなりやることのほうがつまらないということもありますし。ダンスではないことを返してくれる刺激をいかに広げてゆけるかと、模索しています。そういった作業の中で、技術って何だろうと思ったりしています。もちろん、コンテンポラリーダンスの文脈で、脚が上がるような技術だけがダンスじゃないなんてこと、今更言う意味はなくなっている。でも、そうではない独自の技術みたいなこともそれぞれのダンサー、振付家が追い求めていて、そういうものは追求すればある確率は生じてくるわけじゃないですか。その人なりの動き方、語り口など。どこまでそれを固めてゆかず、狭まってゆかずにゆけるかという部分は、先ほどから話して来た創作姿勢とシンクロすると思うんですよ。簡単に言ってしまうと、いかに体が閉じてゆかないかといったことになるのかしら。
+ 今回もGardenでの研究上演会的な初演ですね。お客さんとの出会いに求めるところはありますか?
隅地 初演がGardenというのは、さっきも言ったように、私たちにとって特別な意味合いを持ちます。誤解を受けやすいので、これは本当に言いにくいんですが、市場に広く出す前の内覧会のような場。勿論、私たちの表現に関心を持ってくれている人だけに観て欲しいということでは決してないんですよ。生まれたての状態のものに関心を寄せて、観に来てくれる人の、様々な反応を聴ける場。これも誤解を生みそうなついでに喩えれば、帯とかを作っている人が、お得意様だけを呼んで「次にこんな色あいを出したいと思ってるんですけど、どう思わはりますか?」って聞ける場。通の人向けという意味ではありません。初めてダンスを観た人でも、こちらが言わんとするところにすっと入ってきてくれる方はいますから。ただ、誰でも彼でもという、量としてのお客さんではなく、作品の成長を一緒に見守ってくれるお客さんと、顔が見える関係で意見を交わせる場が欲しいんですね。そうして『10099101』がそうだったように、実際に足を運んでもらったお客さんが漏らされたかすかな反応というものが、最後に一本にまとめるとき、実際、血肉になるんですね。
阿比留 一緒に作ってもらっているような気持ちを持てる場ですね。実はGardenは、踊り手が開けていないと踊れない場所でもあるんです。客席も近いし、照明も日光の微妙な違いで暗転も無い。目の前で観ている人の存在が僕の中にも入ってきている状態で踊らなくちゃならないから、閉じてはいられない。観ている人と関わりを持たないではいられない、すごく怖い場所でもあります。1年に1度、作品を踊ることをそこでスタートしないと、劇場で踊るということもまともにできなくなるような気もしています。視線にさらされている中で、攻撃を仕掛けるという感じではないけれど、受け入れてもらえるように工夫もする。最初の頃はそれが大変だったけど、鍛えられたと思いますよ。お客さんにとっても、戸惑う場所だと思うので、舞台と違う見方を意識してもらえるみたい。通ってくれる人の中には、舞台をよく観る人だけでなく、ボディコンディショニングというワークショップを通じて出会った人もいる。いろんなキャッチの仕方を持っている人が集まってくれています。
隅地 最終的に作品をどうするかというのは、勿論作り手が決定するのですが、その過程でもっと観てくれる人が感想を話し合える、聴き合える場があればいいなと思うんですよね。もの作りのプロセスに、アンケート形式の消費者リサーチとは違うやり方で、使い手の生活感覚を吸い上げるような会社がありますよね。そのように、店頭に並んだものの最終段階だけをとって気に入る気に入らないを決め、作品を観に行く行かないを判断するだけでなく、その過程にいろいろ言え、言ったことが作ったものに反映され得るといったような機会を提供するカンパニーが一つくらいあってもいいかも知れない。
阿比留 今後は足を運んでくれたお客さんに、積極的に何か言ってもらえるように、刺激を与えられたらいいですね。
隅地 とりあえず来てもらって、「何か言って」という甘えた姿勢じゃなくて、思わず何か言いたくなるような刺激を作品に盛り込めたらいいですね。
+ そのような手法に長けたセレノグラフィカさんには、「どの様な見方、受け止め方をしてもいいんです」と言わず、解釈が一つには絶対ならないパズルのように構成しているので「よく噛んでください。咀嚼するほどおいしくなります。」と言い切って欲しいですね。そのような作品を楽しみにしています。本日はありがとうございました。
阿比留 隅地 ありがとうございました。
-
- ■2015.7.9
【暑い夏15】C-1「チョンさん突撃インタビュー!... - 2015年度暑い夏(京都国際ダンスワークショップフェスティバル)でドキュメント・スタッフをはじめて担当したあっちゃん&こいちゃ........
- ■2015.7.9
-
- ■2015.7.9
【暑い夏15】 C-1「チョンさん突撃インタビュー... - 撮影:すやまあつし 京都芸術センターに、雨に濡れながらも笑顔で現れたチョンさん。 あぁ、この笑顔。僕がインタビューしたいなと........
- ■2015.7.9
-
- ■2015.7.1
【暑い夏15】 all「ダンスとは」インタビュー... - 私は言い方によっては、「運動をすることを拒否して生きてきた」。例えば「自転車で冒険にいこう」と言われれば嬉々として出かけるが、........
- ■2015.7.1
-
- ■2015.6.13
関典子×白河直子(H・アール・カオス)ダイアログ ... - ダンス・アーカイヴは、一部の舞踊研究者やクラシック・ダンスマニアの関心事と思われがちだが、じつはコンテンポラリー・ダンスのシー........
- ■2015.6.13
-
- ■2014.8.5
【暑い夏14】A-1・2「新しい風を取り入れたい…... - ここ数年、私はフェスティバル会場で出会った方とのご縁をもとにインタビューしていく「わらしべ長者インタビュー」ということを続けて........
- ■2014.8.5
-
- ■2013.9.29
伴戸千雅子インタビュー>ryotaro[UrBAN... - ダンスのうちそと 京都のアンダーグラウンドシーンを支えるライブハウスUrBANGUILD。音楽だけでなく、ダンス、パフォーマ........
- ■2013.9.29
-
- ■2013.6.18
【暑い夏13】一問多答インタビュー ... - インタビュアー・構成:森下瑶 翻訳:橋本純 皆さんは、空間と身体の関係について意識した事はありますか?おそらく普通の........
- ■2013.6.18
-
- ■2013.6.5
【暑い夏13】わらしべ長者インタビュー(2)... - このインタビューのおおもとの動機は、ダンスへの現在形の関心を、体験レポート以外のやり方でも拾い上げることにあります。基本の質問........
- ■2013.6.5
-
- ■2013.6.3
【暑い夏13】わらしべ長者インタビュー《延長編》 ... - 菅井一輝さんは、本フェスティバルから躍進したダンサーを多く輩出する名古屋のダンスカンパニー、afterimage(アフターイマ........
- ■2013.6.3
-
- ■2013.5.27
【暑い夏13】わらしべ長者インタビュー(1)... - 2年ほど前に偶然はじまった「わらしべ長者インタビュー」。これは、会場内でご縁のあった方に声をかけ、このワークショップフェスティ........
- ■2013.5.27






![伴戸千雅子インタビュー>ryotaro[UrBANGUILD]](https://danceplusmag.com/manage/wp-content/uploads/2013/09/004.jpg)



