未分類
/home/accom/danceplusmag.com/public_html/manage/wp-content/themes/ac_temp_2/content-single.php on line 23
">
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on bool in /home/accom/danceplusmag.com/public_html/manage/wp-content/themes/ac_temp_2/content-single.php on line 23
白井剛×松田正隆『静物画』をめぐるダイアローグ
2010年03月14日
協力:演劇計画2009
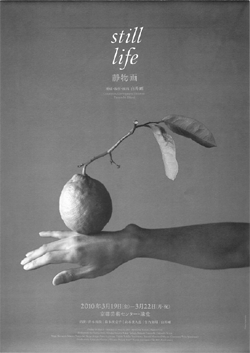
白井剛の新作『静物画 – still life』が京都芸術センター 「演劇計画2009」で製作されている。出発点には、昨年 『blue Lion』で寺田みさこと鈴木ユキオに振付をした際に感じた、踊りを探していく作業の純粋な楽しさがあるという。「ダンスそのものと言えるような、この単純なものだけを扱って作品をつくっていけたら」と語るその心は?
白井がそのテクストに関心を寄せる戯曲家、松田正隆の視線と言葉との往還の中で語ってもらいました。
公演情報
日時:2010年3月19日(金) 19:30
2010年3月20日(土) 19:00
2010年3月21日(日) 15:00
2010年3月22日(月・祝) 15:00
会場:京都芸術センター・講堂
URL:演劇計画2009・公式blogサイト
松田:今回、何を取りかかりに『静物画』を描くんですか?
白井:ダンサーたちとの作業の中で見えてくるものをヒントにしています。例えばそれぞれでウォーミングアップをしている時なんか、ダンスに向かう準備の仕方が各々あるんですが、その座り方、立ち方、伸ばし方すべてが個性的というか、郷に入っている。それは与えられた動きじゃなくて、自分で気に入って長年やってもいるので。そうして気になった動きは、ちょっと真似てみることもあります。この間なんか、手を前に伸ばしてシェイクしているような動きをやって、本人にどういう運動なのか聞いたら、実はお腹の体操だったという…(笑)。作業としては、今回も一対一で動くということをたくさんしています。前に立ってもらった相手に鏡になってもらい、僕はその相手の体を見ながら「首をこうしたらいいかな、いややっぱりこっちのほうが」と動き、相手には僕の体を見ながら「こういうことをしようとしているのかな」と写し取ってもらう。そうしてお互いに相手のフォルムなり質感なりを写し取ろう、もっとはっきり描きだそうとしているうちに、どちらのものでもない振りができてくる。
松田:人を鏡に振付をするっていうのは面白いですね。そうして、自分のものなのか相手のものなのかわからない、どちらのものでもない振りが生まれるという言い方には、非常に惹かれるものがあります。二項のどちらかに浸透してゆくんじゃなくて、第三項のものが現れるというんでしょう? ダンスだけど「その可能性があるんや」って。「親しみ」と「疎遠さ」と言ったらいいのでしょうか。僕は、自分の故郷と初めての場所とを行ったり来たりする中に、何か新しい創造世界みたいなものを求めようと思っているんです。それは、僕にとって親しいものやノスタルジーとどう闘うかっていうことが、自分のテーマとしてあるからなんですが、その時、異境の地にもノスタルジーを感じることは可能かとか、自分の初めて見る場所にどう関わっていけるかっていうことが、自分の生まれた場所、原風景との闘い方に繋がってくるんですね。『blue Lion』でも、実の親子の関係と、そしてそれを舞台でやらなきゃならないってことの緊張をはらんだ関係がありましたよね。舞台って作為的にならざるを得ないものだから、例えば音楽を受け渡すところなんかに感じられた、ふだんの日常の中では意識されない親子のかかわりが、舞台上で行われることで何か新しい世界を生み出すような可能性を感じました。

白井:ドキュメントな部分があっても、舞台にのせるっていうことはフィクション。どうせならもっとフィクションな世界をっていう方向性を持ったところで、その逆の実の父と娘を入れたほうがいろんなものが生まれるんじゃないかということが、『blue Lion』の作戦としてはありました。そのくらいの触れ幅に自分も演じ手も投げ込まれないと、自分の身の中にあるものからは離れられないんじゃないかと思ったんです。僕の持っている父と娘像なんて、本人達にしたらもっと切り離しようがないものだと思います。それを、「これはある物語の登場人物-ギター弾きとダンサー-です」と立たせることで、一瞬でもふっと抽象化された、自分の思い入れからは切り離されたものとして共存する可能性があるんじゃないか、実際そうしないと舞台上で生き延びられないだろう、と。もともとダンサーにしても、ギタリストにしても、人に「何か」を見せたり聴かせたりする職業ではあると思うんですね。勿論、自分の経験なり記憶が何かの糧になっているだろうけど、「自分」を見せたり聴かせたりしているわけじゃなくて、ダンスや曲を届けようとするときに、後ろから自分の記憶みたいなものがエネルギーになっていくっていう関係だと思うんです。そういう風に自分自身を対象化できるような確かなものを与えたときに、やっと光ってくるものがあると思います。なのでドキュメントとしての二人の関係を、自分の中で対象化してもらい、バッハの曲と同じくらい抽象化するにはと考えて振付をしました。
松田:僕の場合は、言語、言葉を書くこと自体が、何か自分のコントロールを超えたものである気がするんですね。言葉で何かを描写する-例えば「あそこの窓の向こうに泰山木の樹があって、 その葉っぱの形は…」ってずっと描いていく時、どんどん自分から離れていく感じはします。まず「泰山木」って名称なんて、僕の生まれる前からあったんでしょうし、それを引用し、それをまた言葉と言葉の間、文と文の間に引用していくわけですから。一方で、自分というか、ここでしか書いてないものに近づいてくる感覚もあります。「外の昼間の灯りの下の樹木」といった、何百回も見たことあるような表現、言葉がそのまま持っているベタな意味と同じにならないようにといったところで。それは自分なりの徴(しるし)、オリジナリティをつけたいっていうことではなく、普遍的に自然と感じられる表現を選ばなかったり、あるいは作品の枠組みの中で言葉の素朴な意味からどういう風に距離がとれるかっていうことを考えたりすると、そうなるんだと思います。つまり、描写をすることには、その言葉自体の力でもって自分から離れていく感覚と、その言葉自体が他にない世界にどんどん入っていく感覚の両方があって、それが創作していて面白いところですけどね。
白井:今言われたような、一個描くと遠ざかったり近づいたりするという感覚は僕にもあります。対象を捉えて自分なりに筆なり踊りなりの行為で描いたとたんに、その対象との距離が歪む。向こうに跳ね返ってゆく、またこっちを見てしまうといった、行ったり来たり感は確かに。言葉で書くほうが、ダンスより外に「出す」っていう感覚が強いかな。ダンスの場合、体の表面からは離れられないので、対象化するのはより難しいんでしょうね。自分で自分自身に振付をするときも、これは描きだすべきだって思える対象をしっかり持っていると、描写はすごく細部にいけるし、何度同じ振付を踊ってもその対象を描くことに熱中している自分がいたりする。逆にそういう対象が曖昧になってきた途端、人に見られている自分とか、人に何かを見せようとしている自分ってところに行ってしまって、「描くべきものがないのにわざわざ人前に立って何をしているんだ」となってしまう。だからそういうしっかりしたものを発見する必要が、ダンサーにとってはあるなと思います。

松田:言葉を置く度に距離感が変わるのと同じように、ダンスでもちょっと離れる瞬間があるっていうのは面白いですね。身体っていうのは、見られているもの、外面でもあるし、自分でも見ることができるけど、目ん玉自身というか、内面とも繋がっていますよね。いつまでたっても「わたしの体」というか。自分を振付する時って、どう…内面がずっとコントロールされているのかな。
白井:実際には、お茶碗を持って水をこぼさないようになるべく速く歩く(笑)といった作業を始めたら、作業のほうに制約が生まれて自分の側は消えていくんです。そうして消えていくことで美しさが出てくる。てことは、振付としてはそういった茶碗の水くらいはっきりした何かが創造できれば、それ以上の意味や物語はいらないだろう。そう思い始めたこともあって、今回は、テーマを持たずにダンスをやりたいと思っています。去年は父と娘の共演という企みがまずあったので、作業の中で振付を見つけたりしながらも、テーマに向けてイメージが膨らんだり繋がったりしたところもありました。その時は物語性ということを結構意識していて、振付の中の場所の移動や距離などにドラマに結び付こうとする作用と、それを裁断していくような作用とを入れていた。でもその間、踊りが何かを説明するための道具になってしまうようなこと、逆にこっちのコンセプトなりドラマなりをつなげていく道具としてムーブメントを都合良く利用するようなことが、ダンサーとして振付家として、ダンスっていいな、ダンスって好きだなと思っている人として、不謹慎というのかな…純粋じゃないなってふと思ったところがあるんです。この茶碗だけでいいのかも知れないのに、歴史上の誰々が使った茶碗ですって言ってみたり周りに壷やお花を置いたりすると、そこにドラマや記号的な意味が生じる。そういった方向に発展させた絵よりも、これだけを描いて、「いいなあ、飾っておきたい」って思える、そういう視点のほうが好ましいなと。なかなか難しいですけど、今回はそんな風にダンスをつくりたいと思っています。
松田:茶碗を持って水をこぼさないようにするときに、視線が茶碗のほうにいって身体が消える。それを振付でもやりたいってことですよね。その時、「水をこぼさないように速く走っている人」っていう意味付けさえ欲しく無くなるんですよね。非常に面白いですね。そこはどういう振付で引き出すんですか。
白井:ワークショップでもやるんですけれど、まずは水の入ったコップなりを持ってみて、感触や重さを味わってから、それを手に持たずにもう一度やってもらうといったことなど。その時、コップを持っている人っていう役を演じたり、コップの重さを的確に説明するっていうのとは、違った次元での印象や感覚が残っている。
松田:その感覚、感触自身が、空間と身体で表現できればっていうことなのかな。
白井:空間にそういったものが出てくるのかどうかはちょっと…。そういった感触は描く対象として内に保たれていたとして、内側にある遠さとか近さっていうところでも動いている。本人が消えた状態の中でそういうことが起こっている人間がいたら、どういう存在に見えるんだろう。そういう存在って強いなとは思っています。スタッフなんかと話していて、「風景の中に人がいるっていう状態じゃなくて、ダンサーの体の中に風景が見えてくる舞台がしたい」ということを言ったんですけれど、「風景の中にいる」っていうのは、たぶんドラマやシチュエーションが生まれることを回避していると言えるんじゃないかな。そうはいっても、舞台に立つだけで何かが生まれてくるわけだけど。

松田:ルドンの版画をたまたま今日見ていたんですが、今の話を聞いて一度お見せしたいなと思いました。版画だから白黒なんです。最初のほうは、人物を光と影で際立たせたり風景や背景から滲み出させたりして、いわゆる自分のイメージの中の目玉を描くときの手段として光を使っている。それが後期のものに、光自身を描こうとしているのか、なんだかわからない不思議な描き方が出てくるんですね。例えば光りを反射している白い紙を触っている手なんだけど、指の先っちょに線がしゅってなって、光が入っちゃっている。それは指なのか光なのか何なのか。そんなことよりも光自体、指自体、あるいはその曖昧になっている部分を描きたいのか。少なくとも何かの対象を出現させるための手段として、白と黒の部分を使っている感じはしない。
白井:光の出てくる線と指はもう等価になっちゃってるんですね。その二つで形が構成されている。
松田:そう。紙の白さが指から漏れている。指は透明のようにも思える。あるいは陽光に包まれている女性の描写なんか、光と女性がもう一緒になっちゃっている。逆に黒のほうにも、闇の中から現れる悪魔みたいな素描画があって、漆黒の中から人間の顔が現れているんだけど、その時に闇と悪魔の領土というか境界が曖昧になっている。そういった時に何か光り自身、闇自身を見るような…、少なくともそれまでの風景描写のような、光で対象を浮かび上がらせるような描き方とは違う見え方になる。それは黒と白のバランス、その境界のところの工夫でできるようなんですね。で、ある出来事を人間って、実はそういう風に見ているんじゃないかって気もするんです。
白井:3年前、ジャン・ジュネの企画をやっている時に知ったんだけど、ジャコメッティの彫刻って、見えるものを見えるとおりにつくろうとしたものらしいですね。なのにあんな細長い人が(笑)出来てくるのが面白かったんですが。ロダンと比べたら全然ボリュームが違うけど、どっちのことを写実と言うのだろうと思ったり。
松田:また恋人と出会う前と別れるときで違う、みたいな言い方もしていましたよね。恋人が去って行くときを描くとあんなに細くなったって、なるほどとも思ったけれど(笑)。そういう恋人との別れとかいった意味づけの部分の中にも、実際なんとも言えない、人に説明できない部分ってありますよね。そっちのほうを描いているのかも知れない。既存の抽象性や普遍的な意味づけがなされ得るものの中にも、えも言われぬ感触って、たぶんあるんだろうなと思います。
白井:描写するって、写真のような写実性と、カメラにはこうは映らないけど目には見えているっていう描き方とありますよね。グリッド引いて描いた写実性ではない、かといって全くの想像の産物でもない、主観的なものと客観的な部分を総動員しないと描きだせないような。今回はそのあたりをもうちょっとやりたいとは思っています。
白井剛(しらい・つよし) 1976年、長野県飯田市生まれ。1996年~2000年、ダンスカンパニー「伊藤キム+輝く未来」の作品に出演。1998年、「Study of Live works 発条ト(ばねと)」の設立に参加。2000年「バニョレ国際振付賞」受賞。2004年、ソロ作品『質量, slide , & .』発表。2006年、トヨタコレオグラフィーアワードにて「次代を担う振付家賞」受賞。2006年、創作ユニット「AbsT」を設立。2007年、第一回日本ダンスフォーラム賞を受賞。2006・2007年、現代音楽カルテット「アルデッティ弦楽四重奏団」とのコラボレーション公演を行う。「演劇計画2008」で『blue Lion』を製作、京都・東京・福岡で上演した。
松田正隆(まつだ・まさたか) 劇作家・演出家/マレビトの会代表。 1962年、長崎県に生まれる。1990年~97年まで劇団「時空劇場」代表を務め、劇作・演出を手がける。1994年『坂の上の家』で第一回OMS戯曲賞大賞受賞。1996年『海と日傘』で岸田國士戯曲賞受賞。1997年『月の岬』で読売演劇大賞作品賞受賞。1998年『夏の砂の上』で読売文学賞受賞。2003年8月よりマレビトの会を結成し、劇作及び演出活動を再び開始。マレビトの会の主な作品に『アウトダフェ』、『クリプトグラフ』、『声紋都市』、『PARKCITY』など。
-
- ■2011.2.17
2011.3.11-13 今貂子+倚羅座 新作舞踏... - [caption id="attachment_7602" align="aligncenter" width="590........
- ■2011.2.17
-
- ■2010.10.31
2010.11.22.~【募集】ココロからだンスW... - 今年で6回目の開催となる、「ココロからだンスWS」。 このワークショップでは、最初に自分の身体が 持っている能力を知ることか........
- ■2010.10.31
-
- ■2010.9.13
2010.09.17~ 「介助者のカラダとこころを... - vol.1 日時:2010年09月17日(金)19:00〜21:30 会場:「パーティ・パーティ」1F(大国町より徒歩3分)........
- ■2010.9.13
-
- ■2010.9.11
2010.10.23-24 花嵐+杉浦梢『アリス・... - 日時:2010年10月23日(土)24日(日)開場14:00〜日没まで / 開演15:00 会場:森邸 京阪本線「香里園」駅徒歩........
- ■2010.9.11
-
- ■2010.9.10
2010.09.10-12 砂連尾理/塚原悠也『S... - 日時:2010年9月10日(金)19:00 2010年9月11日(土)16:00 2010年9月12日(日)15:0........
- ■2010.9.10
-
- ■2010.9.6
2010.09.18 BABY-Q [ INSTA... - 日時:2010年9月18日(土)open 17:00 / start 18:30 会場:名村造船所跡地 がれき前特設ステージ ........
- ■2010.9.6
-
- ■2010.9.1
2010.09.25-26 松本芽紅見 〜群の像〜... - 日時:2010年9月25日(土)19:00 2010年9月26日(日)13:00 / 17:00 * 開演30分前よ........
- ■2010.9.1
-
- ■2010.8.21
2010.09.04 Ensemble Sonne... - 日時:2010年9月4日(土)open 18:30 start 19:00 会場:旧グッゲンハイム邸 料金:予約 ¥2,500 ........
- ■2010.8.21
-
- ■2010.8.21
2010.09.10-12 dots『カカメ』@栗... - 日時:2010年9月10日(金)19:30 2010年9月11日(土)19:30 2010年9月12日(日)15:0........
- ■2010.8.21
-
- ■2010.8.16
【募集】KYOTO EXPERIMENT《10名限... - 世界から舞台芸術の〈現在〉が集う、京都初の国際舞台芸術フェスティバル「KYOTO EXPERIMENT」 。フランス、ア........
- ■2010.8.16






![2010.09.18 BABY-Q [ INSTANT OBLIVION ] in BAKUTO OSucKA 2010 @ 名村造船所跡地](https://danceplusmag.com/manage/wp-content/uploads/2010/09/4.jpg)



